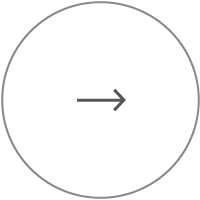今までは土地の境界紛争が生じた場合、時間と費用がかかる裁判等(調停あるいは筆界確定訴訟、所有権確定訴訟)しかありませんでした。しかし、平成18年1月20日に新たな制度「筆界特定制度」が誕生。本制度は、裁判よりもコストや時間を抑えた境界紛争の解決の方法を定めたもので、エスアールパートナーズでは、お客様の状況により最適な方法で問題解決にあたります。
-
境界とは
境界とは、公的に設けられる土地と土地の境目のことをいいます。土地は1区画ごとに地番という番号が法務局から与えられ、「1区画1筆の土地」として登記簿に登記されています。この地番が与えられた土地と土地の境目に境界標識で境界が明確に表示されます。境界は、所有権のある土地の範囲を定めて土地の権利を守る重要な境界線です。境界には、所有権の境を示す「*所有権界」と、地番の境界を示す「*筆界」の2種類があります。

*所有権界
所有権(土地)の範囲を区画する境界線のことをいいます。隣接する土地の当事者間の合意で、境界線を自由に決めることができる境界です。
*筆界
登記された土地の範囲を公的に区画する境界線です。この境界線は公に法務局によって定められるため、隣接する土地の当事者間の合意によって任意に変更することはできません。
境界に伴うトラブル
境界とは、所有権界と、法務局で定められた筆界とは一致するのが基本です。しかし、実際の土地の利用状況や占有状態(時効取得等)により、所有権界と筆界が一致しない場合もあります。この境界の不一致により、当事者間でトラブル(境界紛争)が起こります。このようなトラブルを解決する方法として訴訟を起こす方法がありますが、解決するまでに数年間、その期間に応じて弁護士への報酬という金銭の負担があります。
筆界特定制度と
その目的
「筆界確定訴訟」での*長期にわたる時間と費用を抑えることができる筆界特定制度は、法務局または地方法務局の長から指定を受けた筆界特定登記官が、土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、*筆界調査委員の意見と、当事者の意見を踏まえて、現地で筆界を特定します。新たに筆界を決めるものではなく、調査のうえ、登記された時に定められた元々の筆界を筆界登記官が明らかにすることです。筆界特定制度は行政型ADRの一種でありますが、当事者の調停によって筆界を特定するものではなく、登記所所有の資料や現地の状況など各種の客観的資料をもとに筆界を特定します。あくまでも本制度は公示上の境界を特定する為の行政制度であり、筆界特定書はその証拠となる行政証明であり、行政処分そのものではありません。
-
*筆界特定制度に係る
およその期間と費用申請から筆界特定書交付までの期間はおよそ6ヶ月~10ヶ月を目標としており、費用も訴訟よりも少なくて済みます。
-
*筆界調査委員
筆界と紛争の専門的な知識と経験をもった土地家屋調査士・弁護士・司法書士の中から選ばれる調査委員。
「筆界特定」とは、一の筆界の現地における位置を特定することをいうが(不動産登記法123条2号)、この筆界については、私人間において決められるようなものではなく、一般には公法上の境界を定めるものである為、占有界や所有権界を定めるものではないと解される。すなわち、筆界特定は、過去に定められた筆界を特定するものであり(特定であり確定ではない)、申請のあった筆界の位置が不明であっても、これを新たに形成するものではない(形成権がない)。したがって、筆界特定の申請の目的が、筆界以外の占有界や所有権界の特定を求めるものであったり(所有権が扱えない)、筆界を新たに形成することを求めるもの(未登記土地と未登記土地は申請できない)であるときは、適法な筆界特定の申請とはいえないので、却下される。この制度で筆界が特定されると筆界特定書が作成され、土地の登記簿に筆界特定がなされた旨の記載がされます。
筆界特定制度
による解決
筆界紛争当事者のひとりが話し合いに応じてくれない場合でも、筆界特定制度の申請は一方の土地の所有者等だけですることができます。また、隣接の土地所有者が測量のための立ち入りを拒否している時でも、筆界調査委員の立ち入り権限が認められています(不動産登記法137条)。境界問題に協力的でない相手がいるときは有力な解決方法となり得ます。この制度で特定された筆界をもとに分筆等の登記を申請することができるので、隣地が筆界確定に協力してくれないために分筆・地積更正登記等ができない場合の問題解決に役立ちます。
筆界特定の手続きの流れ

筆界特定の申請
- 書面申請
- 申請人は土地の所有権登記名義人、申請先は筆界特定登記官

受付
- 各法務局本局(筆界特定登記官)にて申請書類の受領
- 申請人の適格、申請内容の審査、申請手数料の納付
- 申請の受理又は却下の判断、適正命令

公告・通知
- 申請受理の旨を公告(法務局本局及び管轄登記所に掲示)、且つ申請受理の旨を利害関係人に通知

筆界調査委員の指定
- 各法務局本局の長は筆界調整委員長を指定

事実・実地調査・
現場測量
- 申請人・利害関係人への事実・実地調整の連絡
- 対象土地の確認・現場調査・資料収集・現況測量

手続費用の予納
- 法務局において手続費用の概算額を算定
- 申請人に手続費用を予納すべき旨の告知及び保管金提出所の交付
- 手続費用の予納金の受領・管理

特定測量
- 申請人及び利害関係者等に立会依頼の通知
- 境界標・構築物・地形等の再調査
- 特定測量の実施

筆界特定登記官に
よる意見聴取の期日
- 申請人及び利害関係人に意見聴取等の期日の通知
- 意見聴取等の開催
- 意見書面の提出

筆界調査委員に
より意見の提出
- 意見聴取の後、筆界特定登記官に意見の提出

筆界特定
- 申請人に筆界特定書の写しを交付
- 利害関係人に筆界特定がされた旨の通知
- 筆界特定がされた旨の公告

記録の保管・公開
- 筆界特定の旨、登記記録の表題部に記録
- 筆界特定書・手続記録を管轄登記所にて保管
- 筆界特定書の写しの交付・手続記録の閲覧に供される。
筆界確定訴訟
との関係
筆界特定制度により特定された筆界に不満・不服のある場合は、当事者が筆界確定訴訟を起こすことが出来ます。この時、筆界特定登記官が特定した筆界と裁判で確定した筆界が異なる場合は判決のほうが効力を持ちます。(不動産登記法148条) 筆界特定の申請において、当該申請の対象となる筆界について、既に筆界確定訴訟の確定判決がある場合や筆界確定訴訟が継続中の場合は注意が必要です。 既に筆界確定訴訟の判決があるときは、筆界特定の申請を認めると筆界を確定する判決が確定しているにもかかわらず、紛争のくり返しを認めることになるので、その申請を却下するものとされている(不動産登記法132条1項6号)。 一方、筆界確定訴訟が提起されており、その訴訟に係る判決が確定していないときは、筆界特定の申請をすることができる。この場合、筆界確定訴訟と筆界特定の手続とが同時に並行して進められるが、実務上は、筆界確定訴訟の係属裁判所の判断により、筆界特定の手続を先に進行させて、筆界特定の結果を筆界確定訴訟の争点整理や事実認定のための資料として、利用することとなります。しかし、筆界確定訴訟の判決が先に確定したときは、筆界特定の申請は却下される事は前述の通りです。
境界紛争
解決機関の選択

境界紛争解
決期間の特徴
-
民間紛争解決期間での境界ADR
当事者・本人同士の納得を得やすい
解決方法の自由選択
-
法務局での筆界特定
所有権の争いは出来ない
6〜10ヶ月で解決
現地における筆界の確認
-
裁判所での民事訴訟
隣人訴訟(人間関係にしこりを残す)
期間が長い
費用が高い
-
「境界標」
あってよかった、
無くて困った日々の暮らしの中で、意識することのない"境界標"。でもいざというときに、自分自身だけでなく子ども、孫の代になって思わぬトラブルに遭遇しない為にも、しっかり確認しておきたい境界標。
境界標にまつわる悲喜こもごもな事例をご紹介します。 

60年後の祖父の気遣い
両親から相続した田舎の土地を不動産業者に下取りとして売却し、新しく都会で住宅を購入することにしました。取引条件が実測となっていたため、隣地との境界を確認することになりましたが、表の道路を除く他は田んぼで、畦道があったりしてはっきりと境界の位置を確認できない状況でした。
そこで、昔からその土地を耕作してた叔父に尋ねると、「祖父の時代(約60年程前)にそこに根石(現在の境界標)を入れていたはずだ。」と教えてくれました。
近隣の立会いの際、その根石の話をしたところ近隣の方たちも相続を受けた方ばかりで、詳しい事情を知る者もいなかったのですが、とりあえずその辺りを掘ってみることにし、スコップで約40センチ程掘ってみると何か当たる物があり、注意をしながら掘り出してみますと屈曲している箇所の全てに角がある石が出ました。当然境界については何の問題もなく確認が出来、無事売買は完了することができました。これをきっかけに私も、自宅にも早速、祖父がしたように境界標を入れようと思っています。

境界石が無くなった!?
今から30年前に土地付きの中古住宅を買いました。購入した当時に境界標がなかったため、分譲地の地積測量図に基づき隣地土地所有者の立会いのもと、境界標を設置しました。
今回、住まいの老朽化で建替えをすることになり、古い住まいを取り壊した時に、工事を担当した工務店がうっかりして、東側の境界標を掘り起こし、無くしてしまいました。東側の土地所有者は、もっと西に境界標があったと主張して譲りませんでしたが、幸い西側の土地所有者との境界標が残っていたのと、東側の土地所有者の東側の境界標が残っていたため、東側の土地所有者に改めて事情を説明し、立ち合いをおこないその結果了解していただきました。一時はこれでご近所とトラブルになり、建築が遅れるのかと心配したのですが、残っている境界標から説明をし、なんとか納得していただくことができました。今後このようなことの無い様に、永続性のある境界標を設置することにしました。

見つからない境界石
役所から、道路の境界を明示するから立ち会ってほしい、という通知を受けとりました。何のことか判りませんでしたが、当日役所の方が来られ、私の家の塀の内側まで道路だと言われました。
十数年前にこの土地を買ったとき、確かに境界石があってそれに合わせて塀を作ったはずだったのですが、いくら捜しても境界標が見つかりません。
いつかの道路工事のときに、工事をした会社が工事上のことから取り除いて元に戻さないままにして、わからなくなってしまったようです。
元々設置してあった境界標の意味をよく知らないで、放置しておいた為に、今日のような次第になったものと、反省しています。

やっかいごとも相続?
郷里で一人で住んでた母が昨年に亡くなり実家を相続しました。そしたら地元の不動産業者から土地を含めて購入したいと言われて、誰も住む人もいないので売却することにしました。不動産会社から境界の立会いをするとのことで帰郷し、実家の隣接者に立会いをお願いしたところ、どうしても西側の所有者の納得を得ることができず、境界確認書を頂くことができません。原因は、西隣の土地の所有者が15年程前に賃貸マンションを建築した時、基礎工事のコンクリート打ちの際に、約40cm程ベースのコンクリートが父の所有地に湧き出したため、当時父と工事の差し止めでもめたことがあって、そのことを根に持っているようです。結果、法外な印鑑代を要求されたり、売りたくても売れない状況となってしまいました。もめた当時は地元の自治会長に仲裁に入ってもらって「建物が完成したら境界標を入れる」との口約束ができたのですが、その後、境界標は設置されることはなく、父は生前「ご近所の手前、裁判までしたくないが、いつまで待っても境界標を入れてくれない。」とこぼしてました。更に、当時仲裁してくれた自治会長も昨年亡くなられ、他には誰もこの事情を知るものはいないようです。ご近所のことでもめるのもイヤですが、だからこそ無理強いしてでも境界標をいれるようにすべきでした。